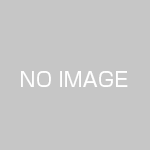ニューヨーク物語33 「私だけの十字架 Ⅲ」
僕が出版元となり、先ごろ無事に完成した渡辺澄晴写真集「New York 1962-64」。この写真集制作に取り組んでいたある朝早く、写真好きのアートディレクター・O氏からの電話が鳴った。新幹線グリーン車の搭載誌での連載仕事(撮影)を任せてもらって以来、個人的な交友も続けてもらってきた方で、僕がニューヨークから帰国して間もなくの頃、二人で渋谷へランチにも行った。
数日前から不在着信があったのだが、O氏との電話は数時間に及ぶことが通例のため、なかなか時間をみつけられずにいた。「棚井にはどうしても会いたくて電話した。もう時間がないんだよ。いま緩和ケアに入っている。」そんな内容だったと思う。いつも冗談交じりのO氏だが、この時ばかりはそんな調子の声ではなかった。すぐにその日の予定をキャンセルして、病院を訪ねた。一緒に行ったイタリアロケで発生した数々のトラブルや、銭湯好きのO氏と一緒に都内のお風呂屋さん巡りをした想い出話で盛り上がった。
2度目に会いに行ったときだっただろうか、写真集を創っていることを伝え、その時に迷っていた表紙とカバーのデザインの相談をした。「Oさん、奥付けにアドバイザーとして名前入れますよ」、そう伝えると「うん、早くできるといいな」と返事が返ってきた。
先日、あれから半年以上の時間が経過してしまったが、やっとのことで出来上がった写真集をO氏に見せに行った。「無」とだけ記された墓石を前に、カバー、表紙、中ページとゆっくりと見てもらった。あの日、O氏に再会できて、アドバイスをもらって、一緒に創り上げた写真集がここにあるということがとてもうれしく、ありがたく感じた。
O氏が残した氏の写真作品ファイルが存在する。そこには幾つかのポストイットが貼られていて、その中の一つは僕が貼ったモノだ。「どれがいいと思う?」いつものように僕を試すかのようなO氏のモノ言い。数十枚の中から一枚を選び出すと「そうだよな〜」と反応しつつ、「その理由は?」と問うような表情を浮かべる(笑)。これまで、何度もこんなやり取りを繰り返してきた。このファイルにポストイットが貼られているのは、O氏が緩和ケアを尋ねてくれた方々に、彼らが欲しいと思う一枚を選んでもらっていたからだ。その写真を自分の手でプリントしてプレゼントしたい、そう言っていたことを僕は忘れられない。最後の力を振り絞って訪れたイタリアで撮影したこれらの作品には、これまで以上に教会の写真が多かったように記憶している。自らの運命を十字架に重ねていたのかも知れない。ポストイットには何の表記もなく誰がどの写真を選んだのか全くわからないのだが、「必ず、それぞれの方に渡しますよ」、僕は最後にO氏にそう言葉をかけた。
その後、何度となくO氏の奥さまから連絡をもらっている。O氏が、愛機(カメラ)を僕に託すと言っていたというのだが、まだ受け取れていない。何故なら、今夜にも「トスカーナ(イタリア)でいい写真を撮ったんだよ、見に来いよ」と電話がありそうな気がしているからだ。
 帰り道、この近くに事務所兼自宅があり、大学時代にしばらくのあいだ助手をさせてもらい、プロの厳しさを教えてくれた建築照明撮影を専門とする写真家・K氏に連絡をしてみた。昨年末にもこの周辺に用があった際に携帯電話に連絡をしてみたが、ちょうど外出先ですぐには戻れないというので、数分間の会話をしたのみだった。昔からの変わらぬその声のトーンに、電話の向こうの柔和な笑顔が想像できた。かつて、僕がニューヨークから数日間一時帰国した際に偶然にも新宿のヨドバシカメラで再会し、飲みに行くか!ということになったりするなどの出来事もあり、完全帰国した時にもすぐに連絡をしたのだが、オリッピックに向けた建築業界の好景気にK 氏の仕事も忙しくなっているということでタイミングを逃していた。
帰り道、この近くに事務所兼自宅があり、大学時代にしばらくのあいだ助手をさせてもらい、プロの厳しさを教えてくれた建築照明撮影を専門とする写真家・K氏に連絡をしてみた。昨年末にもこの周辺に用があった際に携帯電話に連絡をしてみたが、ちょうど外出先ですぐには戻れないというので、数分間の会話をしたのみだった。昔からの変わらぬその声のトーンに、電話の向こうの柔和な笑顔が想像できた。かつて、僕がニューヨークから数日間一時帰国した際に偶然にも新宿のヨドバシカメラで再会し、飲みに行くか!ということになったりするなどの出来事もあり、完全帰国した時にもすぐに連絡をしたのだが、オリッピックに向けた建築業界の好景気にK 氏の仕事も忙しくなっているということでタイミングを逃していた。
今回はその携帯電話が通じないので、数十年振りに事務所の留守番電話にメッセージを残した。それでも何かに呼ばれる気がして、都心のいい場所にある事務所なので立ち退きにもでもあっていないかと、近くまでへ行ってみることにした。実は、懐かしさのあまり、昨年末にも不在承知で建物の前まで足を運んでいたのだった。
この日の気温は34度、最寄り駅まで着いた頃には汗だくで、ボーっともしていたが、気がつくとまた事務所の方向に脚が向いていた。事務所の建物周辺をウロウロしたためだろう、街角スナップ撮影のためにカメラを持って住宅街を歩いているときに感じるまるで「不審者」を見るよう近隣住人の目線と同じモノをすぐ横の道路工事のガードマンからも感じた。突き刺さる視線に擦過傷のような痛みを感じつつ、名刺に自分の携帯電話番号を書き入れて扉の隙間から差し込んだ。すると、1時間もしないうちに折り返し電話がかかってきた。「なんだよー、入れ違いかぁ、でもこの後のKさんの予定がなければいまからでも戻るか」そう思いながら電話に出た。しかし、それはK氏本人ではなく、奥さまからの悲しい知らせだった。言葉を失ったが、少しして僕はこう言っていた。「こんなときですが、Kさんが撮影した写真やネガはきちんと管理していますか?」。そう尋ねたのは、今度K氏に会ったら、かつての想い出話や、近況報告、そしてもうひとつ、仕事以外の作品も含めた氏の作品と名前を後世に残すべく撮影情報を整理しておいて欲しいと伝えるつもりだったからだ。
ニューヨークから帰国して以来、ひょんなことから、いや、宿命なのか運命なのか仕組まれたのか、写真の著作権と写真作品の保存活動に関わっているが、そこには、「自身の作品制作との時間的バランスをどう取るのか」という難しさがある。しかし僕は、戦後の写真界をつくりあげた木村伊兵衛氏と土門拳氏の写真魂をそれぞれの門弟から学んだという、その幸運にも深い感謝をしており、現在、木村氏の弟子であった田沼武能氏が会長として、リーダーとして行なっているこうした活動に参加する事が、ほんの少しでも先人たちへの恩返しになるならと心の隅で思ってもいる。
K氏のことを聞いた時、この活動から得られる事柄やそこから沸き起こる意識が、またそれを生かすことが、K氏への恩返しになるのではないかと瞬時に考えたのだと思う。写真家・K氏の生き様をもっと知り、記録に残したいと。これが今の僕にできることだと。帰路の電車内で、突然Kさんの顔が浮かんできた。声が聞こえてきた。涙が止まらなくなった。
O氏の墓前で、ほんの少しのあいだ十字架から降架されたように感じたが、すぐにまたそれは昇架された。
2018.8.21
photo&text: 棚井文雄 / Fumio TANAI / HJPI320610000334